落語には、よく酒飲みが登場します。落語家にとっては、おいしそうに酒を飲む様子や、ひどく酔っ払った人(大虎)などを声色やしゃべり方を変えて演じるところが見せ場。どんな大虎になるのかも、落語家によって違います。(「Newsがわかる2023年7月号」より)

【英文】
Kuma returns from a holiday morning bath to see his next-door neighbor trying to throw away a sea bream’s head and tail. She tells him that it’s her cat’s leftover.
He goes home with the fish, and covers it with a wooden lid, with its head and tail sticking out, which makes it look like an entire fish. Just then, his friend comes over and sees it. Delighted that they can share the fish over sake, he goes out to purchase a bottle. When he comes back, Kuma decides to put the blame on his neighbor’s cat for stealing the fish. Having heard that, his friend goes out again saying “my head’s filled with that fish!” In the end, Kuma drinks up the entire bottle of sake.
【和訳】
「猫の災難」という題名ですが、実際は猫というよりは大虎(酒飲み)の噺。
休日に朝湯から戻ってきた熊さん、隣人がタイの頭としっぽを捨てようとしているのを目にする。聞くと、飼い猫の食べ残しだとのこと。
それをもらい、うちでタイの体(身)の部分を木のふたで隠すと、まるで丸ごとのタイのように見える。そこへちょうど遊びにやってきた(年上の)友人(兄貴分)、タイを食べながら酒が飲めると大喜びで酒を買いに行ってしまう。仕方ないので熊さん、帰ってきた兄貴分にタイの身は隣の猫に盗まれたと(うその)言い訳をする。それを聞いた兄貴分、「俺はもう頭の中がタイでいっぱいなんだ!」と言いながら、タイを買いに表へ出る。すると今度は熊さん、お酒をみんな飲み干してしまう。


「猫の災難」の噺を英語で表現すると、日常会話で使えるセンテンスがたくさんあります。特に大事なものを見ていきましょう。

ふたの下に大きなタイが丸ごと1匹あると思い込んだ兄貴分が酒を買いに行く時、「ウロコもちゃんと取っておけよ」と熊さんに言います。 それに対して熊さんは「うん、全然問題ないよ!」と答えます。それはそうです、身もないんですから、ウロコがあるはずがありません。

覆水盆に返らず、の意味。せっかく酒を買ってきたのに、タイが隣の猫に取られてしまったと聞いて、落ち込む兄貴分に熊さんがかける言葉。「どの口でそれを言うか」というせりふではありますが、よく使われるフレーズです。日本語と英語でほぼ同じ言い回しながら、水とミルクが違うというのが面白いですね。

2度目、兄貴分がタイを買って帰ってくると、熊さんが酔っ払って真っ赤な顔をしています。「俺が留守の間に飲んだんだろう!」と言われた熊さんは「違うの、飲んだんじゃないの。(猫に瓶を倒されて)畳にこぼれたお酒を吸ったの!」と答えます。そして上記の「お酒というものは飲むよりも吸う方が酔うね」という言葉が続きます。大好きなせりふです。

英語版「猫の災難」の下げ(オチ)のせりふです。「これまでお前が言ってたことはみんなうそじゃねえか!」「いや、うそじゃないよ、ちょっとインチキなだけ」という感じです。魚のFishと、怪しい、うさんくさい、というFishyがかかっています。

一説によると、猫が日本に入ってきたのは今から2000年ほど前の弥生時代だったそうです。江戸時代においても猫というのは、犬と並んで人間のよき相棒でした。
ただ猫の場合は純粋なペットというよりも、ネズミ退治という実用的な役割も期待されていました。農家などでは蚕をネズミから守るために猫を飼ったり、「猫絵」という、猫の絵をおまじないで張っていたりしたそうです。この噺で猫の病気見舞いにタイをもらえたのも、それだけ大事な存在だったからかも。

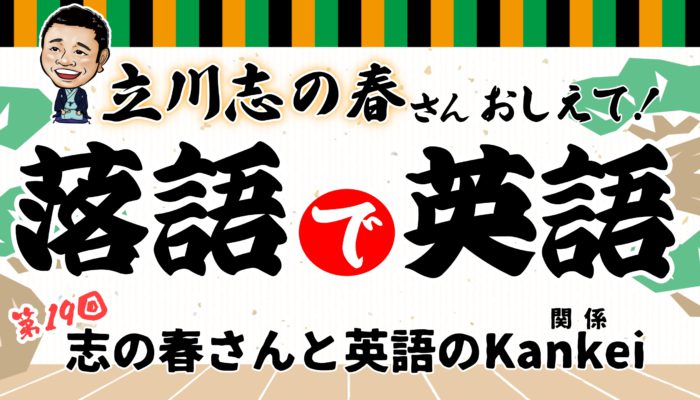

-447x255.jpg)